「撮影を始めてから3.11を経験しました。山形では、ガソリンもない、まともに食べものを買うことができないという状況が1ヶ月も続きました。その時はじめてインタビューした人たちが話していた『不作のときに命をつなぐ芋だった』といった言葉が実感をもって受け止められました」
30代になったばかりの渡辺智史監督は、試写会上映後、そう語りました。
「よみがえりのレシピ」は、昨年の山形国際ドキュメンタリー映画祭でも上映されました。映画祭には行っていたのですが見る機会をえず、東京での上映を心待ちにしていました。
その前に、この映画の下敷きになっている「庄内パラディーゾ」という本を読んでいたこともありました。
「ここにしかないんだから」「これで漬ける漬けものが食べたいって言われるから」
そんな理由で、誰に言われたわけでなく、それがお金になるわけでもなく、それでも淡々と種を採取し、 自分ができる範囲で在来作物を育て続けてきた人たちが描かれています。
綿々と続く暮らしの中に物語があり、随所に心に残る言葉がありました
まずは出だし、この映画の画面の明るさが新鮮でした。
伝統的な日本映画や農村を描く場合にありがちな暗さやしめっぽさがありません。根性、努力、精神性といったこと、イデオロギー的なことにもふれていません。
監督の「知りたい!」というシンプルな思いや、インタビューを続ける中で感じ考えていくうちに醸成されてきた熱い思いは、彼自身のキャラクターなのか(お話していても静かなる情熱という感じで、たった一度会っただけでまだ映画を見ていもいないのに、この人が作るものならときっと共感してくれると思う人たちに声をかけて一緒にみに行きました)
、派手に語られることはないし、おしつけと感じられるものも一切なく、でもだからこそ、登場人物たちも自然に心を開き、思いの深いところを言葉にしてくれたのだと思います。
山形は夏は暑く冬は寒い。熱帯性の作物もあるけれど、これらは人が手をかけなければ冬には死んでしまう。一方でその作物が死んでしまえば人は食べるものがなくて生きていけなくなってしまう。
「作物と人との共存関係」
その言葉がとくに印象に残りました。
ただアル・ケッチャーノだけでなく、、、
今や多くの人が知るようになった、アル・ケッチャーノのシェフと山形大学の研究者とがタッグを組み、今までになかった食べ方を提案し、その魅力を引き出してみせることによって在来作物への関心が高まり、その栽培が復活してきています。
奥田シェフをよく知る人から話をきくと、彼がどれほどの情熱をもって山形の在来作物の継承や山形の食をよくすることに力を入れているのかがわかります。
ただアル・ケッチャーノで食べるから、奥田シェフの腕があるからおいしい!というところを超えて、地元の人を中心にどんなふうに食べていくのかが研究され、地元のレストランや家庭料理での広がりがでてくることこそがこれからとても大切になってくると思います。
渋谷ユーロスペースで10月20日より上映
「よみがえりのレシピ」は、素直に「応援したい!」と思える映画でした。
10月20日からは渋谷のユーロスペースでの上映も決まっており、また自主上映用にDVDやブルーレイの貸し出しもあります。
一人でも多くの人にこの映画を見てほしいと思います。
山形だけでなく、全国各地で、誰に知られることもなく今日も淡々と在来作物の種を守っている人たちを応援する動きにつながればと思います。
 サカイ優佳子
Yukako Sakai
Food Activist
サカイ優佳子
Yukako Sakai
Food Activist































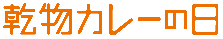






コメントをお書きください