種屋に生まれたという著者、西川芳昭氏の専門は農村開発、農業生物多様性管理。種子調達や品種管理の調査研究を手がけてきた。
2017年2月。種子法の廃止が閣議で了承されたことをきっかけに、種子と人との関係に興味を持つ人が増えてほしいという思いで書いた本という(その後、種子法は2018年4月1日を持って廃止された)。
種子法とは何か?
種子法とは、戦後の食糧難の中、日本が国としての主権を取り戻してすぐのタイミングで、1952年に制定された「主要農作物種子法」の略称だ。
稲、麦(大麦、ハダカムギ、小麦)、大豆について、国の管理下で種子の生産を行うための法律で、二度と国民を飢えさせないという思いの下に制定されたと考えられている。
種子法があることで、日本では、各地域に適した品種の種子が安定的、比較的安価に農家に供給されてきた。
一方で、種子法が存在しても、品種が集中し、自給率も上がらず、という事実もまたある。
また、種子法があるために、農家が自分で品種を選ぶ力を奪ってきたというマイナスの側面もあると著者はいう。
日本の農業ならではの特徴を活かして
「日本の農業は北米やオーストラリアのように、本来的に食料輸出を目的とした植民地型の農業ではなく、土地に根ざして地域の小さなニッチ市場を得意とする農業の歴史を持っており、低価格・大量生産を競争力の根源と考えるフォーディズム的な農業とは異なる」とする農業経済学者、河村能夫氏の意見が紹介されている。私もこの意見に同意する。
著者も同様の意見の下に、種子法廃止の理由として、本来日本農業の強みではない「輸出振興」があげられていることに疑問を呈している。
輸出競争力のあるごく一部の農家や農業法人だけが生き残るような農業は、日本の食料や農村の持続性にとっては問題ではないか、と。
種は誰のものか?
また、政府が、「民間による種子や種苗の生産供給の促進、国や都道府県が持つ知見を民間に提供し、連携して品種開発を進める」とすることは、そうした素材を下に開発された種子や種苗を知的財産権として登録し、企業が囲い込むことで、農業生産や研究開発に使えないようにすることも可能になる現状に、著者は危機感を表明している。
災い転じて福となる?
著者の主張でおもしろいと思ったのは、種子法が廃止されたことを不幸と見るのではなく、むしろ、チャンスでもあるのではないかとしていることだ。
今まで多くの人が意識すらしてこなかった、種子法の存在とその果たしてきた役割に気づき、種子について、農業のあり方について、食についてを考えるきっかけとなることで、未来はむしろ明るくなる可能性があるとして、そうした潮流とも言えるべき動きの紹介に紙幅を費やしている。
そして、
地域関係者による遺伝資源の管理、
自分が食べるものは自分で決めるという「食料主権」の考え方、
家族型農業、地域に根ざした農業、趣味の園芸家などが自家採種を行い、周りの人がそれを食べることで支えること、
などによって、一部企業や国だけがプレーヤーだけではなく、すべての人が種子をめぐるシステムに関わることで、人類の共通財産である種子を次世代に継承していけるはずとする。
日々の暮らしの中で、特段の注意を払うことなく過ごしている種子。
法律の廃止に目くじらを立てるよりも、「自分にもできることってなんだろう?」という姿勢でいたいと考えさせられた。

 サカイ優佳子
Yukako Sakai
Food Activist
サカイ優佳子
Yukako Sakai
Food Activist































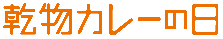






コメントをお書きください