今は作家として生きる筆者は、北大法学部出身。出版社に勤務するも上司と喧嘩して一年で失職。偶然にも近いご縁で屠殺場の作業員になる。そんな著者の自伝的エッセーである。
まずは、私を含む、肉が好きという人にはぜひ読んでほしい本だ。

なぜこの本を手に取ったのか
10月のシェアReadingの会は「肉を食べる」をテーマに開催した(その様子はこちらをご覧ください)。
そのテーマで本を探している時、検索で上がってきたこの本の表紙にまずは惹きつけられた。
刃物を持ち、立つ男一人。
少し寂し気でもあり、でも内面からにじむ誇りのようなものが感じられる。
著者の略歴をみると、かつて10年半屠殺場の作業員として働き、今は専業作家とある。
なぜ?
これだけでも興味深かった。
たまたま置かれた場所でも、誰に褒められなくても、、
屠殺という職場は、日本においては、まだまだ偏見の目で見られることが多い。この本の中では「ここに勤めていたら結婚ができない」と辞めていく若者たちのことも描かれている。
そんな職場で働く大卒の著者は、「おめえみたいなヤツのくるところじゃねえ!」といきなり先輩に怒鳴られながらも、その場、その日、その時に集中して包丁の研ぎ方を、とどめの刺し方を、皮のはぎ方を、肉のさばき方を身につけていく。
それとともに周りの人たちが著者を見る目も変化していく。
技を身につけていくその中で培われる自信がその筆致から感じられる。
肉を食べるなら、屠殺というプロセスは無視できないはず
私たちが食べる肉は、誰かが屠殺しなければ「肉」にはならないのに、日本では、なぜその部分は触れてはいけないもののように扱われているのだろうか。
シェアReadingの会の参加者からは、「ドイツなどヨーロッパでは肉屋さんは尊敬される職業なんですけどね」という意見も出ていた。
この本で描かれるのは屠殺のプロセスがオートメ化する前の時代のもので、著者をはじめ作業員たちはケガの危険と隣り合わせでカラダを張って働いている。
著者が初めて牛をハンマーで息絶えさせるくだりでは、思わず息を止めて読んでいる自分がいた。
肉を食べるということは、こうした仕事があってこそなのだということを、今一度自分に言い聞かせる。
こんな人に読んでほしい!
この本は、多くの人にとって屠殺をめぐるあれこれ、肉を食べるということについて考えてみるきっかけになると思う。
一方で、今の仕事に意義が見出せないと感じて悩んでいる人にもまたぜひ読んでほしいと思う。
10年半に及ぶ屠殺場の作業員として働いた日々における著者の成長の記録でもあるこの本は、働くこと、技を身につけていくことからくる自己肯定感、自負に溢れている。
目の前のことに集中し、精進することで身につけた技は、誰にも奪われることのない宝物。この本を読むと、今やるべきことに、自分の全力で取り組んでみようとも思うのである。
 サカイ優佳子
Yukako Sakai
Food Activist
サカイ優佳子
Yukako Sakai
Food Activist































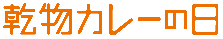





コメントをお書きください